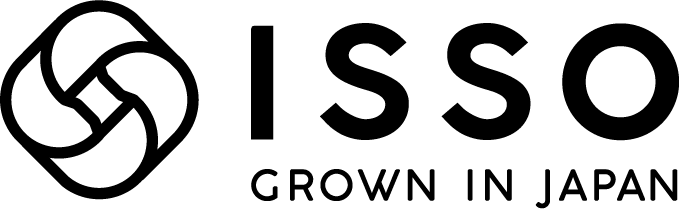ISSO TEA SCHOOL vol. 6 自然のめぐみと、それに向き合うつくり手たち
日本茶が私たちの手元に届くまでには、いくつもの丁寧な手仕事が重ねられています。ISSO TEA SCHOOL vol.6では、「自然のめぐみと、それに向き合うつくり手たち」についてお話ししたいと思います。

土づくりから始まる、時間のかかるお茶づくり
この物語は、日々変わっていく自然と真摯に向き合い、熟練した匠の技をもって心を込めてお茶を育てる営みから始まります。
茶の苗を植えてから十分に育ち、茶葉として収穫できるまでには5〜8年の歳月が必要です。加えて、農薬や化学肥料に頼らない有機栽培を開始するにも、技術と時間が必要です。有機栽培で質の良い茶葉を作るには、「通常の1.5〜2倍の手間がかかる」とも言われています。
そうした時間を重ねた上に、ようやく今年のISSO TEAの一番茶は芽吹きます。

「ISSOゆたかみどり煎茶」に使われる茶葉は、「かぶせ」と呼ばれる被覆栽培で育てられています。茶畑一面寒冷紗などの遮光資材をかけ、一本一本の茶枝に手作業で固定する作業は、体力と根気の要る大変な作業です。このひと手間によって茶葉は日光を遮られ、旨み成分であるアミノ酸の一種・テアニンをたっぷりと蓄え、豊かな味わいを備えていき、茶葉が鮮やかな緑色に育ちます。
「荒茶」と「仕上げ」という工程
日本茶の製造には、「荒茶」と「仕上げ」という、二つの大切な工程があります。この工程の積み重ねこそが、お茶の味わいに奥行きを与え、香りを引き立て、ひとしずくの余韻にまで物語を宿らせるのです。

荒茶とは、摘み取ったばかりの生葉を蒸し、揉み、乾燥させた段階の、いわば“味わいのもと”がぎゅっと詰まった茶葉です。茶葉素材そのもののポテンシャルがそのままに現れています。丁寧に育てられた荒茶が、今年もまた、茶師のもとへと届き始めています。

茶師は届いた荒茶一つひとつの香りと味、その年の茶葉の個性を最大限に引き出すために、微細な違いを見極め、火入れ・焙煎の温度や時間を調整しながら、仕上げの工程を担います。香り、旨み、余韻 - 一杯の中に宿る自然の風味は、この仕上げの技でさらに磨き上げられていきます。細部にまで心を配ることで、一杯のお茶に奥行きと豊かな表情が生まれるのです。
ISSOの一番茶
現在、抹茶の人気が海外でも爆発的に高まり、抹茶の原料となる碾茶の需要も例年にない伸びを見せています。
その中で、変化する自然に向き合い、質の高い有機煎茶や抹茶を作り続けてくださるつくり手の方々に、私たちは深い敬意と感謝の気持ちを抱いています。

自然とつくり手が生み出した素材の豊かな美しさを、さらに極めた美味しさへと磨き上げる茶師の匠の技。今年も心をこめて、お茶をお届けしてまいります。